「憐み」と「優しさ」
先日、佐賀にお住いのお友達のヒーラーさんが、ヒーリングとは別に、新しいお仕事をされるというご連絡をいただきました。
障害を持たれている方々のためのケアホームをこれから経営されるそうで、お友達のその決意を、私もとても嬉しく思いました。
私たちは人のために何かをする時、喜びや満たされた気持ちを感じます。
それは、私たちが自分で命を生み出したのではなく、これまで命ちを分かち合いながら受けてきたという記憶が残っているから。
たぶん、人間というものは自分のことだけを考えて生きると、苦しみの内に人生が進んで行くのだろう。
だから、他者のことばかり気にかける人は、気がつかないうちに自分のことも気にかけて見ているのだろう。
だから、困っている人を見ると、私たちは心を揺り動かされるのです。
その感情を「憐み」と言います。

「ささやかな憐みでも、
世界をあたためることができる、
少しであっても正義をもたらすことができる」(教皇フランシスコ)
とういう言葉があります。
「憐み」という言葉は、上から目線で気の毒に思う、何かをしてあげるというようなイメージもあるかもしれません。
でも、そうではないのです。
辞書には、気の毒に思う、同情する、と説明される前に、賞美する、愛すると書かれています。
新約聖書のなかの「憐み」という言葉は、もともとギリシャ語の「スプランクナ」という言葉で、これは「内蔵、はらわた」を示すものなのだそうです。
「憐れむ」の動詞「スプランクニゾマイ」は、直訳すると「内蔵が揺り動かされる」ということになります。
「憐れむ」とは、単純に「かわいそう」という意味ではないのです。
気の毒な人に出会って、どうしようもなく心が痛んで、たまらなくなって、その人のものに駆けつけていかざるを得ないような気持ちになる。
そのような心の様子を表す言葉なのです。
そこには、相手が気の合う人だからという勘定も、自分の利益になりそうな人だからという駆け引きも、少しも働いていないのです。
見て見ぬふりができなくなって、たまらなくなって駆け寄っていこういこうとする、心の動きだけがあるのです。

仏教では、「施しは無上の善根なり」という言葉があり、人に施すということは、それを必要とされる人のために心をこめて捧げることだといわれます。
自分の善根を磨くために、お釈迦さまは三つの法を説いています。
財施とは、困っている人に食べ物、お金、どんな小さなものでも差し上げること。
法施とは、心の貧しい人、心の飢えた人、人の道を知らない人に、法を説いてあげること。
無畏施とは、身寄りのないお年寄り、ひとりで死を恐れている人、自身を失い、劣等感に悩まされている人、そういう人たちを勇気づけてあげること。

人生とは、本人の希望であり、自由であり責任だから、と言って距離を置くのは簡単ですし、その判断が正しいこともあるのかもしれません。
でも、本人が少しでも希望をもっていたとしたら、私はなんとかしようとする気がする。
本人たち以上になんとかしようとする気がする。
本人たちの無意識まで感じて、何とかしようとする気がする。
自分の気持ちを抑えて、人に優しさを行うことができるのは、人間だけなのです。
物が足りなくても満足して、欲望を満たせなくても我慢できるのは、他の動物にはない、人間だけに与えられた能力。
どんな自分でも、受け入れてくれる、できることがある、望まれて生きている。
ただ、そのことを気づかせていく。
正しく在るために、自分の良心に従う道に進む時、憐みというものが生まれるのでしょう。
「憐みには二つの面があります。
憐みは、他者に与え、他者を助け、他者に仕えることですが、
それだけでなく、
ゆるし、理解することでもあります」
(使徒的勧告)
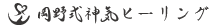











この記事へのコメントはありません。